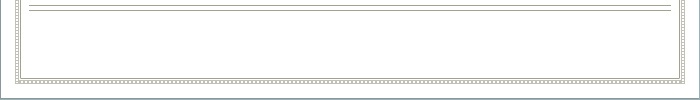教室沿革


教室沿革

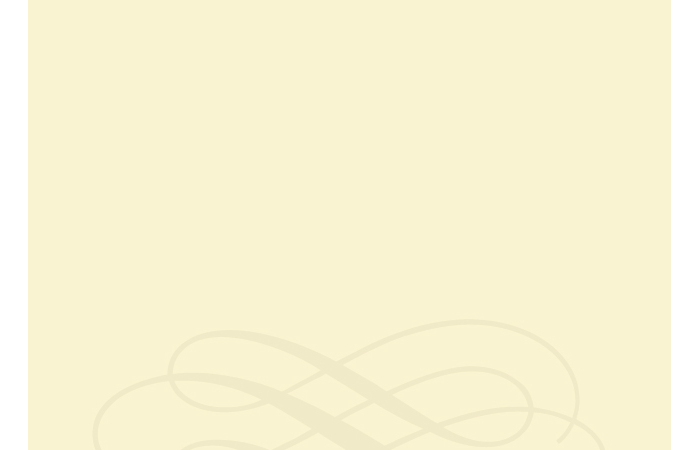
1967(昭和42)年6月1日、北海道大学に歯学部が創設された。翌年の1968年4月1日には、歯学部内に口腔生理学講座が正規に設置され、初代の中村治雄教授(1968年4月1日〜1977年3月、北海道大学医学部卒)、第2代の亀田和夫教授(1977年9月〜1996年3月、東京医科歯科大学医学部卒)、第3代の赤池忠教授(1996年10月1日〜2007年3月、東京大学医学部卒)、第4代の舩橋誠教授(2008年2月16日〜現在、岡山大学歯学部卒)と引き継がれて今日に至っている。
1997年から2007年は、大学院重点化と国立大学の独立法人化という2大改革が敢行された激動の時代であった。2000年4月、大学院重点化に伴う改組により、北海道大学大学院歯学研究科は大講座制に移行し、旧口腔生理学講座は口腔機能学講座の中の一つの教室となった。2004年4月の独立法人化に伴い、教室名を口腔生理細胞情報学教室と改称した。当時の教室スタッフは吉村啓一助教授、鎌田勉助手、野田阪佳伸助手であった。その後、野田阪助手は2001年3月31日に歯学部内で配置換えとなり移動した。
2002年3月に吉村啓一助教授が定年退職し、後任として鎌田勉助手が助教授に昇任した。2000年4月1日より、村井恵良助手、2002年8月より平井喜幸助手が採用され、2004年4月30日に村井恵良助手が久留米大学に転任し、2004年10月より黄田育宏助手が採用された。2005年3月、鎌田勉助教授の定年退職に伴い、後任として、2005年4月1日に岡山大学大学院医歯学総合研究科脳神経制御学講座口腔生理学分野から舩橋誠助手が助教授として赴任した。2006年から歯科麻酔学教室の黒住章弘助手らと、「悪心・嘔吐の中枢機構と麻酔薬」に関する研究に着手した。
2007年3月31日に赤池教授が定年退職し,名誉教授の称号が授与された。同年4月より教育職の呼称が改正され、助教授は准教授、助手は助教へと変更された。教授不在のまま暫くの間、舩橋准教授によって教室が運営され、公募による教授選考を経て、2008年2月16日付けで舩橋准教授が教授に昇任し、教室名も口腔生理学教室と改められた。舩橋教授と共に平井助教と黄田助教が協力して教室の新体制がスタートし,生理学・口腔生理学の講義・実習等の学部教育を担当した。舩橋教授の研究テーマは「摂食行動および悪心・嘔吐に関わる中枢神経機構」であり,脳スライスを用いた電気生理学的な手法や免疫組織化学的手法を用いて単一ニューロンレベルで神経活動の解析を行っている。平井助教は分子生物学的手法を用いてエナメル芽細胞に関する研究を行っていたが,最近は舩橋教授の研究テーマである摂食調節の中枢機構について解析に着手し,大学院生と共に行動実験を開始している。また,黄田助教は磁気共鳴画像装置を用いた脳機能解析に関する研究を行っていたが,2009年3月に東京都精神医学総合研究所へ転出した。黄田助教の後任として,2009年4月に前澤仁志助教(北海道大学歯学部卒)が赴任し,脳磁計を用いた上位中枢の非侵襲的解析を開始した。2015年2月に久留和成助教(鹿児島大学卒,九州大学大学院卒)が着任し,電気生理学の専門家としての経歴を生かして当教室での研究を開始した。2020年1月末日をもって久留助教は任期満了のため退職した.2020年2月から乾賢准教授(大阪大学人間科学部卒)が着任した.乾准教授は行動生理学の専門家でフロリダ州立大学での研究経験も生かして本研究室での活躍が期待される.2020年9月末日をもって平井助教は退職した.2020年10月から吉澤知彦助教(北大歯学部卒)が東京医科歯科大学から着任した.吉澤助教は北大テニュアトラック制度での採用で今後の活躍が期待される.
2007年4月より臨床系教室(予防歯科学教室,高齢者歯科学教室,口腔顎顔面外科学教室,小児・障害者歯科学教室,口腔機能補綴学教室,口腔診断内科学教室,名寄看護大学)から大学院生および社会人大学院生を若干名受け入れている。これまでに11名の大学院生が学位を取得した。目下,電気生理学と行動科学の手法を用いて悪心・嘔吐および摂食行動の中枢メカニズムについて解析を進めている。